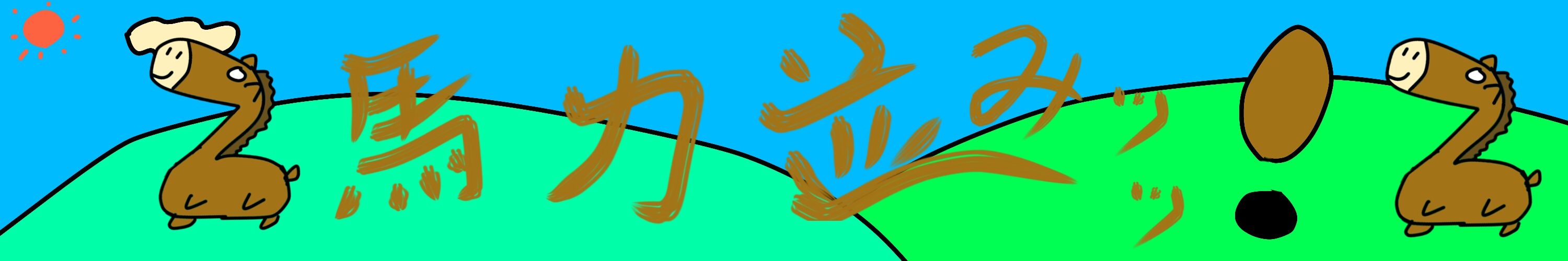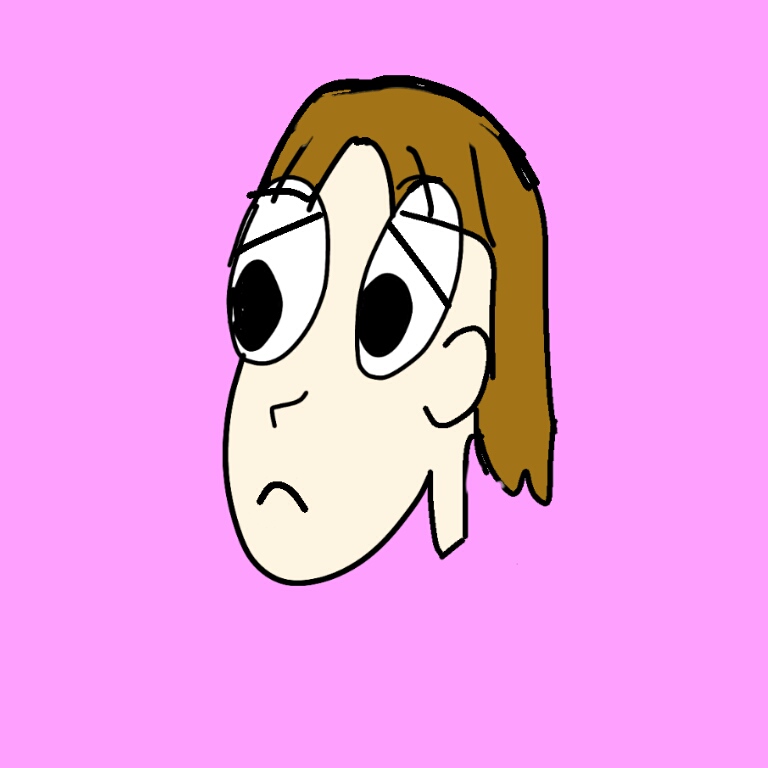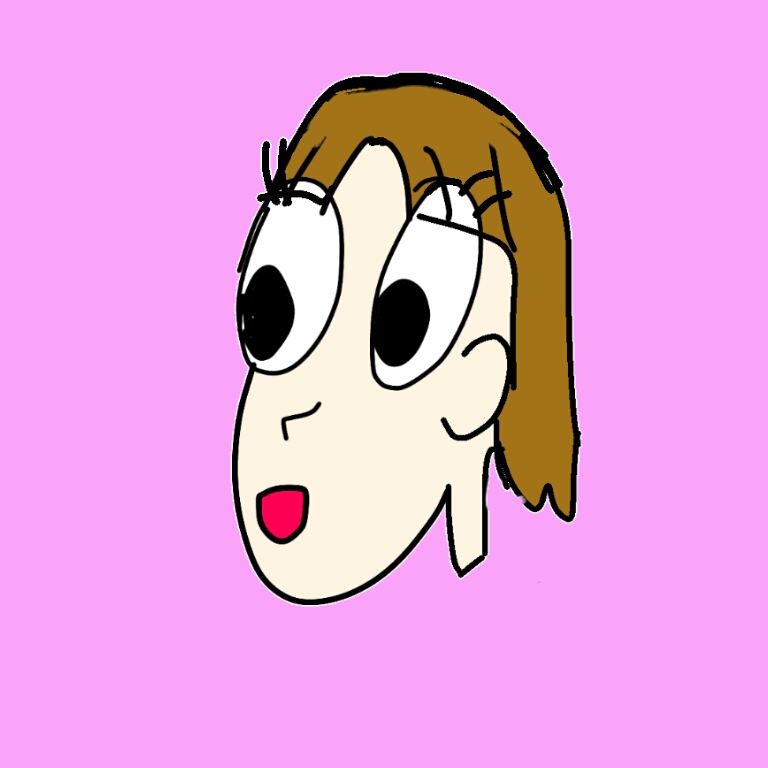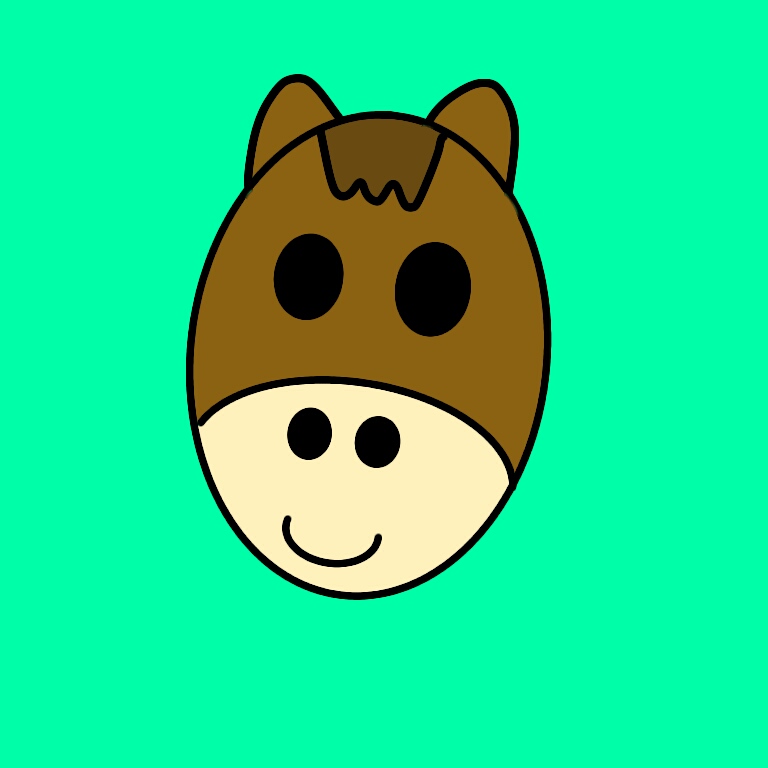ある日のサカモト家
(でも、そんなお金どこにあるの、とは言えず…。)
というわけで、子供たちがのびのび生活するためにもマイホームが必要なんじゃないかということで、マイホーム建設を検討することになりました。
サカモトフタマです、みなさんこんにちは。
まずは全く知識がないため、近所の住宅展示場へ赴き、雰囲気をつかもうということになりました。
なんとなしに一条工務店の展示場にフラッと入ってみたところ、とんでもない目に…。
この記事で伝えたいこと
住宅は性能

丁寧に営業の担当者が一つ一つ説明をしてくれました。
全く住宅に疎い僕でも、一条工務店の住宅は比較的割高だというウワサは聞いたことがあります。
担当者に聞いてみたら確かに割高だという。
気のせいか担当者の目が一瞬キラッと光ったような…。
営業さんの営業魂に火を付けてしまったのか、そこから怒濤の営業トークが始まりました。
ポイントは次のとおり
- 住宅は性能が第一
- 高気密高断熱の住宅はランニングコストがかからない
- 一条工務店の家は全館床暖房だけであったかい
- 後のメンテナンス費用がかからない材料(メンテナンスフリータイルやシロアリ対策木材)により建設後のメンテナンス費用をカット
- 結果、トータルコスト(死ぬまでのかな?)はローコスト住宅よりもコストが安く住む
- そんなこんなで、近年の新築件数は他のハウスメーカーをぶち抜いて、一条工務店がトップらしい
- オプションで夢発電という太陽光発電で売電してウマー
営業さんが言うにはザックリとですが、こんなことでした。
話はとても長くて半日近くつぶれてしまったけど、とにかく勉強になりました。
疲れさせて他のハウスメーカーの話を聞かせない作戦なのかもしれません(笑)。
確かに営業さんの話を鵜呑みにすると、一条工務店で建てた方がお得だと思います。
お値段は多少割高ですが、その分建てた後の費用を抑えようというのが一条工務店のコンセプトらしいです。
新築時の費用ばかり気にしていましたが、とても勉強になりました。
僕はアラフォーなのでどんなに長くみても、死ぬまでに60年間も住めればいいことになります。
よし、60年のトータルコストが安い家、うん、コンセプトは決まった。
嫁はもうすっかり一条工務店にしてしまおうと言っています。
他のシステムを模索する
住宅展示場で話を聞くのは一条工務店の営業さんの作戦通りもうコリゴリでした。
半日も話を聞いてたら疲れはててしまいました。
子供にトミカをプレゼントしてくれましたが、半日頑張ってトミカ一台では正直キツイ。
しかも、なんとかパンフレットがわりのタブレット端末を貸付たくてしょうがないのか、しきりに持っていけ持っていけとうるさい。
もう一度この怒濤の営業トークを聞くのはウンザリだったのでなんとかなんとかしつこいのを断って帰ってきました。
もう、話を聞くのはこりごりなので、ネットで似たような省エネシステムはないものかと模索してみました。
断熱性能について調べていたら「ネオマフォーム」という断熱材を旭化成建材株式会社が作っていて、「ネオマの家」というコンセプトハウスを作っていることがわかりました、特設サイトまであります。
ネオマの家
 (出典 旭化成建材株式会社 あたたか族 快適空間研究所)
(出典 旭化成建材株式会社 あたたか族 快適空間研究所)
ネオマの家とは簡単にいうと(多分)次のとおり
断熱性能を極限まで高め、太陽光などの自然エネルギーをなるべく取り入れることによって、省エネルギーで快適な住環境を整えること
冬は太陽光の暖かさを取り込み、夏は太陽光からの熱を防ぐ。
矛盾しているように感じますが、それを実現しようとしています。
こういったデザインをパッシブデザインというそうで、確かに実現できれば理想的な住環境を整えられそうです。
究極のパッシブデザイン住宅は、真夏も真冬も空調器具を使用せずに快適な室温を保つことができるのかもしれませんが、理論的には可能かもしれませんがなかなか実現は難しそうです。
そこで、なるべく自然エネルギーを取り入れつつ、快適な住環境を整えるために天井エアコンと床下エアコンの2台で快適な室温を保ち続けるというシステムのようです。
このシステムであれば、一年中快適な室温を保ち続けることができ、高気密高断熱かつパッシブデザインにより冷暖房コストを極限まで節約することができそうです。
 (出典 旭化成建材株式会社 あたたか族 快適空間研究所)
(出典 旭化成建材株式会社 あたたか族 快適空間研究所)
まとめ
さて、自分がマイホームなんて夢にも思っていませんでしたが、今回色々勉強してみて最近の戸建住宅の流行り?のようなものがつかめてきました。
今は住宅は性能で選ぶ時代
新築時のコストだけではなく、その後のコストまで考える
省エネルギー住宅
といった感じでしょうか?
もちろん、性能が良ければそれに越したことはないのでしょうが、当然コストが高くなります。
今後は、実現可能な性能や我が家での優先事項、それに予算を考慮しながら無理のない範囲で新築計画をたてていかなければなりません。
新しい家と言われればワクワクしそうですが、なかなか道のりは遠く険しくなりそうです。
とりあえず、もう少し勉強しながらどのような住環境が必要か考えていきたいと思います。